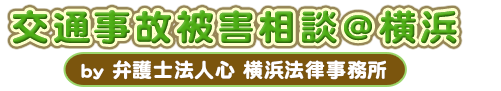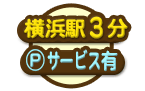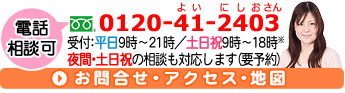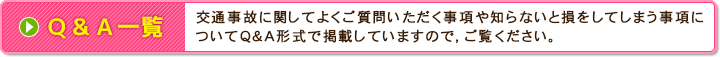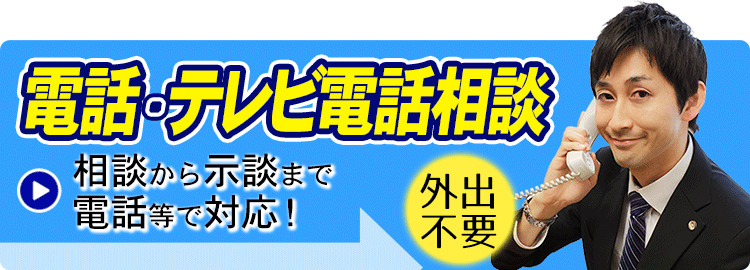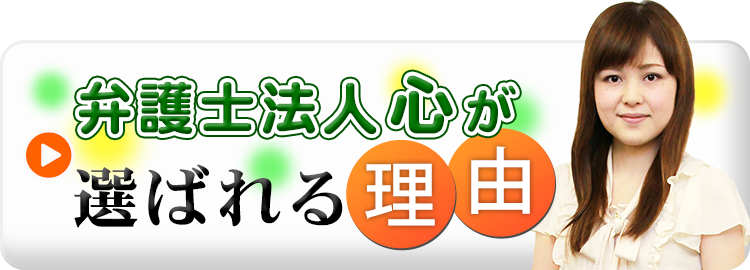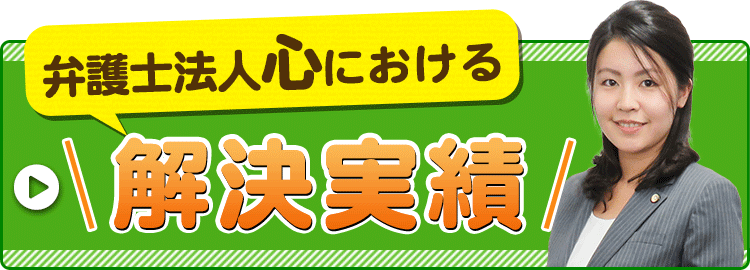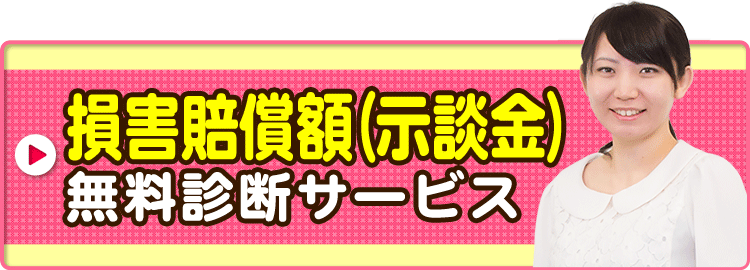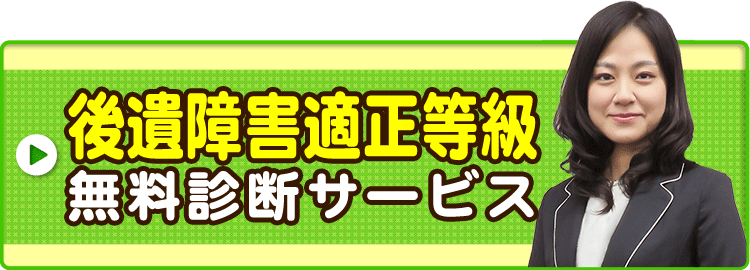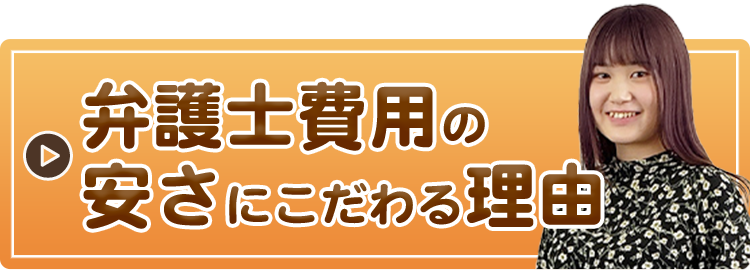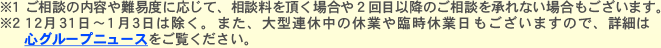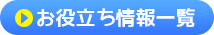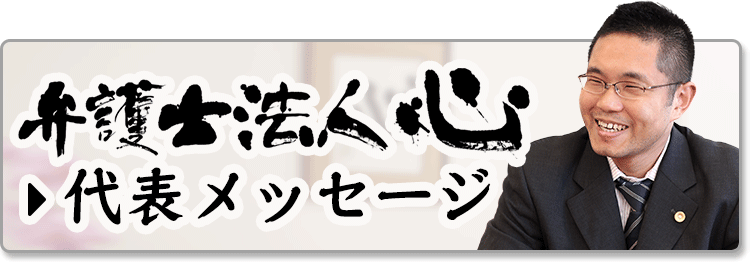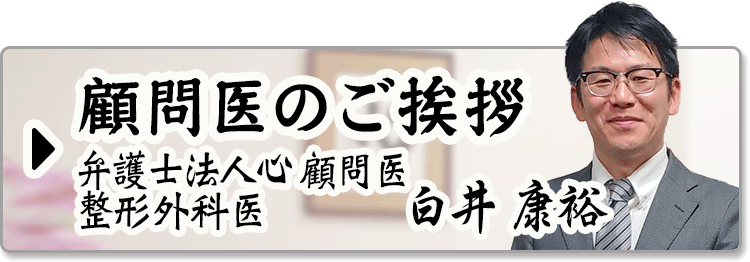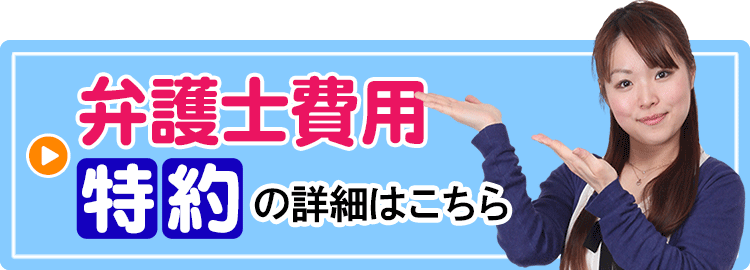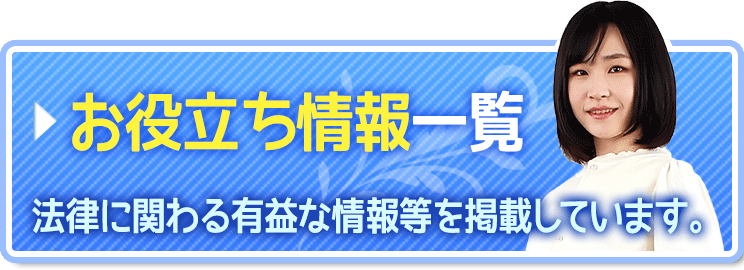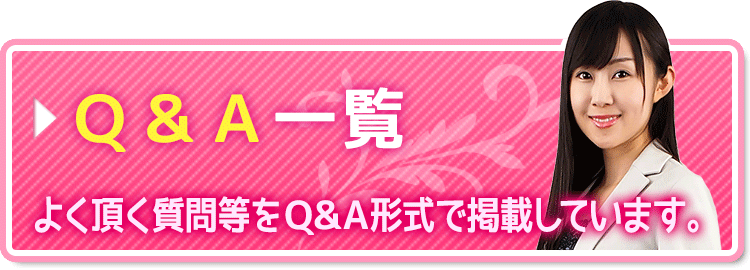交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
1 交通事故における慰謝料
交通事故における慰謝料とは、事故によって負傷した被害者の方が被った精神的な苦痛に関する損害を金銭に換算したものです。
被害者の方が味わった精神的な苦痛といっても、これは目に見えるものでなく、客観的な金額を算出することは不可能と言えます。
また、苦痛の感じ方は人によって異なるため、例えば、同じような事故態様で、同じような怪我をして、同じような治療をした場合であっても、加害者側から慰謝料100万円を支払うと提案されたときに、「そんなにもらえるのか」と感じる方もいれば、「それだけでは納得できない」と感じる方もいるなど、様々です。
ただ、多くの方は、「100万円という金額が妥当なのか、低すぎるのか、分からない」と仰います。
そのため、加害者側から提案された慰謝料の妥当性が分からず、示談書に署名することに躊躇してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのようなときは、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、被害者の方にとって最適な慰謝料かを判断することもできますし、必要に応じて加害者側と交渉することも可能です。
2 交通事故における慰謝料を算出する基準
交通事故における慰謝料は、慰謝料が発生する原因によって、死亡慰謝料、後遺症慰謝料、傷害慰謝料に分類されます。
これらの慰謝料を客観的に算出することは不可能なので、加害者の保険会社や裁判所は、慰謝料を算出するにあたって、慰謝料の種類ごとに一応の目安ともいうべき基準をもっています。
慰謝料を算出する目安となる基準は、以下のように分類されます。
①自賠責基準(自賠責保険会社が用いる基準)
②任意保険会社基準(加害者の任意保険会社が用いる基準)
③裁判基準(交通事故裁判において裁判所が用いる基準)
慰謝料は、通常、①自賠責基準≦②任意保険会社基準<③裁判基準、の順で高額になります。
弁護士は、③裁判基準を用いて慰謝料を算定するため、弁護士が交渉すると、加害者の保険会社が提示した慰謝料が増額する可能性が高いのです。
特に、死亡慰謝料、後遺症慰謝料、傷害慰謝料は、被害者の方の生活状況、後遺障害の内容、入通院状況等、様々な個別の事情を考慮して算出されるべきであるのに、加害者の任意保険会社が提示する慰謝料は、弁護士が算定する慰謝料より著しく低額にとどまるケースがよくみられます。
3 交通事故の慰謝料については当法人にご相談ください
当法人では、加害者側保険会社から提示された示談金の内容が妥当かどうか、無料でチェックするサービスを行っております。
交通事故の慰謝料でお悩みの方や、適切な慰謝料の金額を知りたいという方は、どうぞお気軽にご相談ください。
加害者が保険に加入していない場合の慰謝料請求
1 加害者が任意保険未加入、自賠責保険は加入の場合

⑴ まずは自賠責保険金から
加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険に慰謝料を請求していくことはできます。
しかし、自賠責保険金には上限額がありますし、自賠責保険金は、治療費、交通費、休業損害などの項目を全てひっくるめての自賠責保険金の上限額の範囲内での支払いしか受けることができません。
傷害部分の上限額は120万円が限度です(被害者側に過失が7割未満の場合)。
そのため、裁判基準の慰謝料を受け取るためには、他に請求していく必要があります。
⑵ 加害者本人への請求
加害者は、任意保険の加入の有無にかかわらず、法律上の賠償義務を負いますので、加害者本人へ、慰謝料を請求できるのは当然です。
しかし、高額の場合や、そもそも任意保険に加入していないような方は、資力が乏しいのが一般的であるため、加害者から十分な慰謝料の賠償を受けることができる可能性はそこまで高くないのが一般的です。
⑶ 加害者本人の勤務先への請求
加害者本人が、仕事中であったり、会社のロゴ等が入っている車を運転して事故を起こしている場合などには、加害者の勤務先へ使用者責任を問うことで、慰謝料を請求することはできます。
⑷ 被害者側の保険を使用する
ご自身やご家族の方が加入している保険で、人身傷害保険、無保険車特約等の特約に加入していれば、その特約を使うことで慰謝料を受け取ることができます。
しかし、これらの特約は約款で決まっている金額でしか支払われないため、訴訟をするなどしない限り、裁判基準の慰謝料を受け取ることはできないことがあるので注意が必要です。
2 加害者が自賠責保険にも加入していない場合
加害者が強制保険である自賠責保険にすら加入していない場合には、政府保証事業の利用というのも考えられます。
政府保証事情とは、自賠責保険の対象とならないひき逃げの事故や、自賠責保険に加入していない車が加害車両となった事故の場合に利用することができます。
ただし、健康保険や労災でカバーしてもらえなかった部分に限られます。
交通事故被害者の方が慰謝料について弁護士に相談する利点
1 利点その1:高い基準の金額でまとまりやすい

⑴ 慰謝料の3つの基準
慰謝料には、いくつかの基準があります。
金額が低い順に紹介していくと、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判基準(訴訟基準や弁護士基準とも表現されることもあります)となります。
弁護士が介入しなければ、通常③裁判基準での一番高い金額での解決はありません。
⑵弁護士を介入させないと通常一番高い基準での解決は難しい
ご本人様だけでの交渉ですと、一番低い①自賠責基準での回答や、自賠責基準よりは高いけれども裁判基準よりは低い②任意保険会社基準どまりでの金額となってしまいます。
一番高い基準での賠償金獲得を目指すのであれば、弁護士を介入させての保険会社との交渉をお勧めいたします。
2 利点その2:慰謝料の計算方法を解説してもらえる
⑴ 算定方法の解説
弁護士に慰謝料についてご相談していただくことで、①自賠責基準の慰謝料の算定方法や、③裁判基準での慰謝料の算定方法を教えてもらうことができます。
⑵ ①自賠責基準の算定方法
例えば、自賠責基準での慰謝料の算定方法は、①総通院日数×4300円(令和2年4月1日以降発生の事故の場合)か、②実通院日数×2倍×4300円のどちらか低い金額で計算されます。
ただし、自賠責保険金の傷害部分は、慰謝料以外にも治療費や交通費、休業損害などの項目を全部含めて120万円が限度です。
⑶ ③裁判基準での算定方法
ア 赤本Ⅰと赤本Ⅱの違い
裁判基準にも様々あるのですが、ここでは赤い本基準で解説します。
赤い本基準にも、むちうちの基準である赤本Ⅱ基準と、むちうち以外の基準である赤本Ⅰ基準がありまして、金額が高いのは、赤本Ⅰ基準となります。
例えば、通院6か月の場合、赤本Ⅰ基準の場合は、116万円となっており、赤本Ⅱ基準の場合には、89万円となっております。
イ 示談段階では裁判基準の8~9割とされることも多い
先ほどお示しした、通院6か月の赤本Ⅰ:116万円、赤本Ⅱ:89万円という金額は、あくまでも裁判をした場合に裁判所が認定してくれる金額であるため、示談段階では、それよりも1~2割低い金額で提示されることも多いです。
慰謝料の提示額に納得いかない場合は弁護士にご相談を
1 提示額は低いことが多い

交通事故の治療が終わってから約1、2か月後、相手方保険会社から被害者の手元に、示談の提案書が届きます。
そこには、相手方保険会社が支払う慰謝料の金額が記載されています。
しかし、そこに記載された慰謝料は、弁護士から見ると低い金額であることが多いです。
保険会社は営利企業なので、できれば低い金額で示談しようとすることが少なくありません。
これに対して、被害者の立場からすると、相手方保険会社が提案した金額が妥当かどうか分からないため、そのまま示談に応じてしまうことが多いです。
しかし、被害者側に弁護士が就いて、弁護士が相手方保険会社と慰謝料の交渉をすると、相手方保険会社は裁判所基準で慰謝料の支払いに応じることがほとんどです。
2 慰謝料の支払基準
慰謝料の支払基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判所基準の3つがあります。
①自賠責基準とは、自賠責保険が用いている慰謝料の計算基準です。
日額4300円×通院期間で計算した金額と、日額4300円×実通院日数×2で計算した金額のいずれか低い方が、自賠責基準で計算した慰謝料となります。
②任意保険基準とは、任意保険会社が独自に作成した慰謝料の計算基準です。
任意保険基準は、自賠責基準よりは高く、裁判所基準よりは低い金額となることが多い計算基準です。
③裁判所基準とは、裁判所が用いている慰謝料の計算基準です。
裁判所基準のうち代表的なものは、いわゆる「赤い本」に掲載されている基準です。
赤い本には、別表Ⅰと別表Ⅱという基準が掲載されています。
別表Ⅰは、骨折をした場合など他覚的所見がある場合に用いられます。
別表Ⅱは、むちうちなど他覚的所見がない場合に用いられます。
通院慰謝料は、原則として、通院期間に応じて計算されます。
③は①②よりも高い金額になることが多いため、弁護士が相手方保険会社と交渉することによって、慰謝料が増額することになります。
3 当法人に相談
当法人には、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しております。
慰謝料に関してお悩みがある方は、お気軽に当法人までお問合せください。