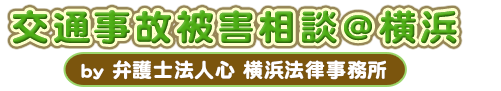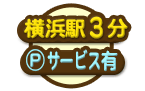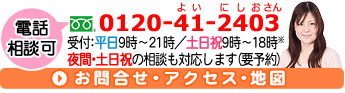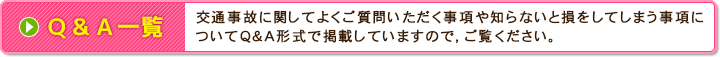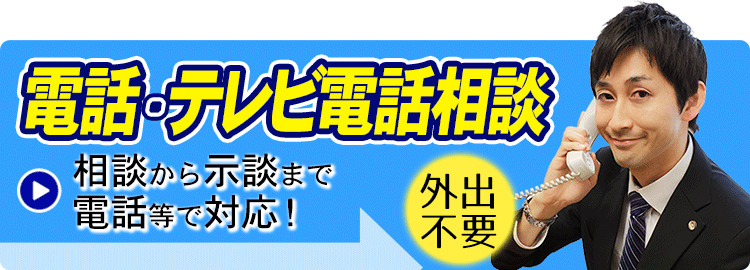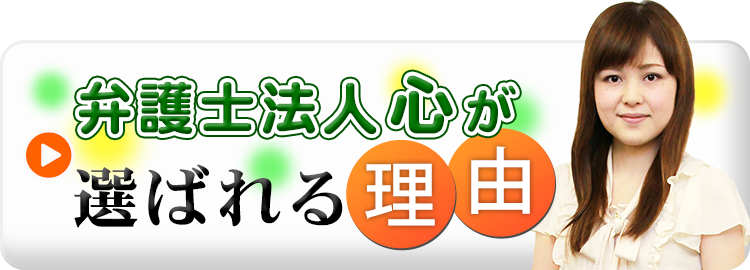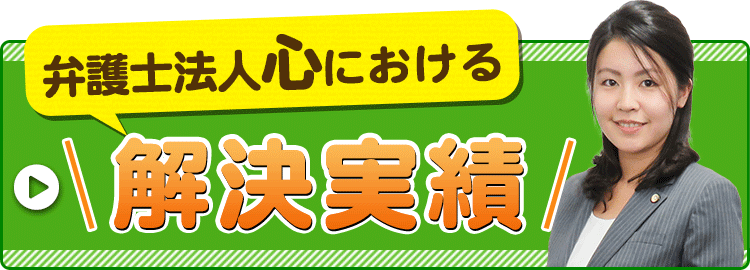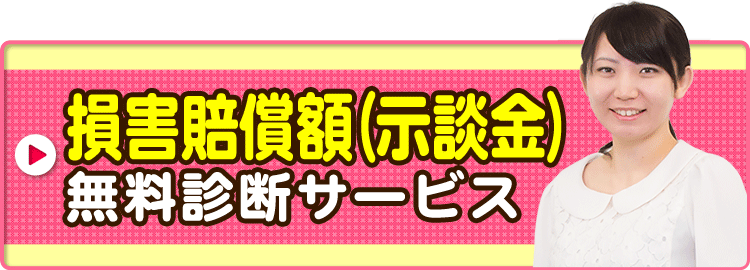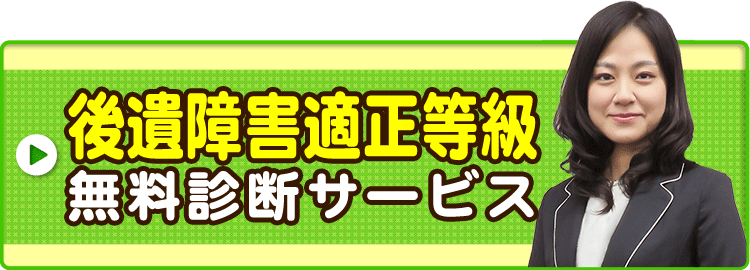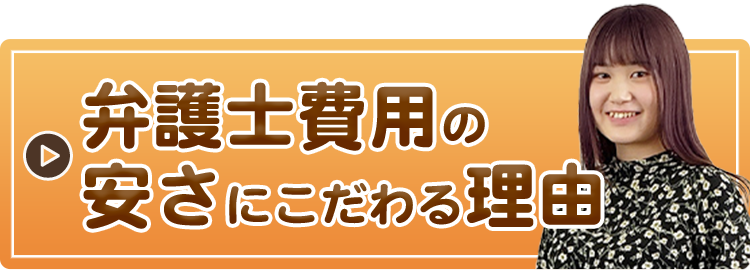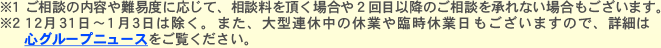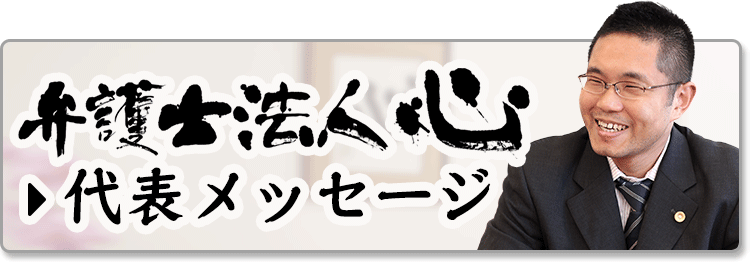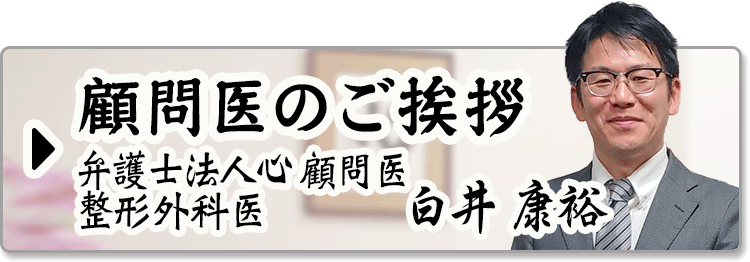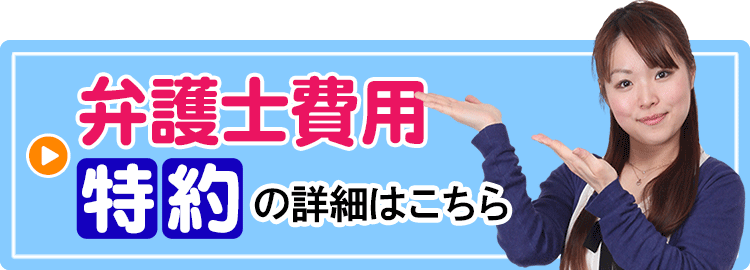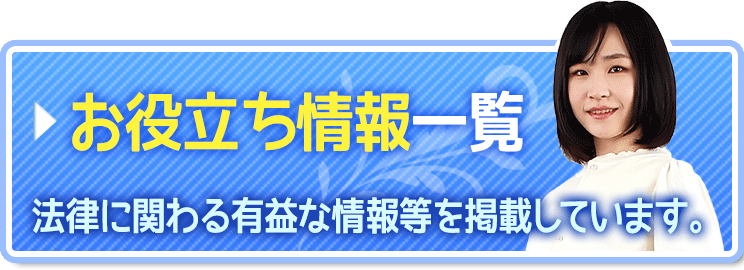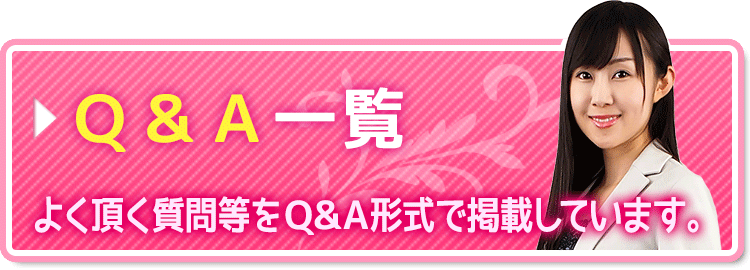高次脳機能障害での症状固定の時期について
1 一般的な症状固定の時期
高次脳機能障害における症状固定の時期は、一般的には、早いと事故から半年程度、通常で1年前後、少し長いと、1年半や2年といったケースがあります。
2 症状固定の時期までに気を付けておくべきこと
⑴ 無条件に医師任せにしておくべきではない
高次脳機能障害の場合には、脳神経外科等での診察を受けておくだけでは、適切に後遺障害等級認定評価をしてもらえない場合も少なくありません。
なぜなら、脳神経外科の医師であれば、どの医師でも、適切な検査をしてくれるとは限らないからです。
⑵ 高次脳機能障害についての判断材料
高次脳機能障害に関しては、程度が軽い場合には、なかなか通常の健常者と変わらない場合が多いことから、医師も、高次脳機能障害としては特に気にする必要のないレベルだと判断してしまい、適切な検査を受けることなく症状固定の時期を迎えてしまい、後遺障害等級認定審査の際の判断材料が乏しいということにもなりかねません。
この場合には、もし、何らかの高次脳機能障害の等級が認定されたとしても、裁判などで、相手方から等級が適切でないと争われる可能性も高くなってしまいます。
高次脳機能障害で看護が必要になった場合の賠償について むちうちで弁護士をお探しの方へ